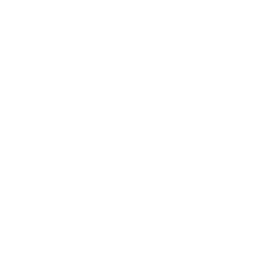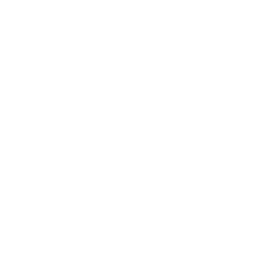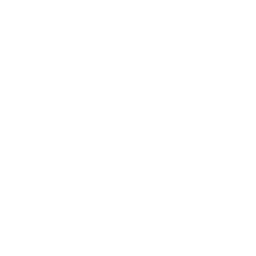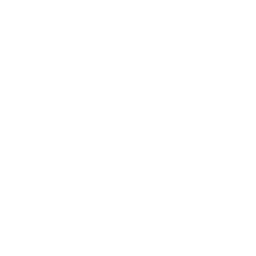AHA/ACC高血圧新ガイドラインが示す「早期介入」と「目標の厳格化」
米国心臓協会(AHA)と米国心臓病学会(ACC)は、成人の高血圧(BP)に関する新しいガイドラインをこの8月に発表しました。この改訂は、最新のエビデンスを組み込み、高血圧管理の標準を、「より早期の治療(Earlier Treatment)」と「より厳格なBPコントロール(Tighter Control)」へと明確にシフトさせるものです。
ガイドラインの共著者であるカーン医師は、心臓、脳、腎臓の健康を考慮すると、「より低い血圧がより良いという非常に強力な証拠がある」ため、「血圧治療をより早く開始し、より低い目標を目指す」べきだと述べています。高血圧の定義(正常、高値、ステージ1、ステージ2)や推奨される第一選択薬は2017年のガイドラインから変更されていませんが、治療目標値や介入戦略には、患者ケアを変える可能性のある重要な更新が含まれています。
日本の薬剤師として、この国際的な潮流を理解し、患者様への服薬指導や生活習慣指導、また医師への情報提供において、これらの最新の知見をどのように活用すべきかを探ります。
JAMA Medical News
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2841006
1.目標値の厳格化と「Treat Earlier」戦略の拡大
新しいガイドラインの最も重要な変更点は、治療目標値のメッセージの強化と、薬物療法を開始するタイミングの早期化です。
- より低い目標値への強い奨励
心血管疾患(CVD)リスクが高い高血圧患者に対するBP目標は、引き続き収縮期BPが少なくとも 130 mm Hg未満と推奨されていますが、新しい表現では、120 mm Hg未満の達成が奨励されています。
ガイドライン執筆委員長であるジョーンズ医師は、「エビデンスは明らかに120が心疾患、脳卒中、腎臓病の減少により優れていると示している」と、この厳格化の理由を説明しています。目標BP達成の判断は、少なくとも2回の受診における2回以上の測定値に基づく必要があり、単一の測定値に依存すべきではありません。集中降圧療法に関連する有害事象は「まれであり、通常は軽度」とされていますが、個々の患者の選択には臨床医の判断と共有意思決定が引き続き重要です。 - ステージ1高血圧への薬物療法の早期介入
薬物療法の開始時期も早期化されました(Treat Earlier)。
さらに、臨床的CVDはないが糖尿病や慢性腎臓病(CKD)を有するステージ1高血圧の患者に対しても、直ちに投薬を開始することが推奨されています。
ステージ1高血圧で、臨床的CVDがなく、10年リスクが低い患者は、生活習慣の改善に取り組みますが、3〜6か月で目標に達しない場合は降圧薬の服用を開始すべきとされました。以前のガイドラインでは、この低リスク集団はステージ2になるまで薬物療法を待つことが推奨されていました。
2. 併用療法の推進とリスク評価ツールの更新
新しいガイドラインは、治療効果を最大化し、服薬遵守(アドヒアランス)を改善するための具体的な戦略を示しています。
新しいリスク計算ツール「PREVENT」の採用
治療開始や目標決定のためのCVDリスク評価には、従来のプール化コホート方程式(PCEs)に代わり、AHAの新しいPREVENT(Predicting Risk of CVD Events)リスク計算ツールが採用されました。
PREVENTは、腎機能や、アテローム性動脈硬化性CVDに加えて心不全のリスクも評価項目に含める点が改善されており、より正確なCVDリスク予測が可能とされています。PREVENTでは、10年予測CVDリスクが7.5%以上であればリスク増加と定義されます(これはPCEsでの10%リスクに相当します)。
ステージ2以上における単剤療法の回避と配合剤の推奨
診断時にステージ2高血圧以上の患者に対しては、「単剤では不十分」であり、最初から複数の降圧薬の併用療法を開始することが推奨されています。これは、併用療法によって患者がより早く目標に到達し、それを長く維持できるという過去5年間の治験結果に基づいています。
さらに、アドヒアランスを改善する目的で、広く利用可能な一錠に2種類の薬剤を組み合わせた配合剤(Single-Pill Combinations)の使用が推奨されています。薬剤師は、服薬回数が減ることによる利便性向上を患者指導で強調し、配合剤の利用促進に貢献できます。
3.認知症予防の強調と診断の精度向上
高血圧管理は、脳の健康、特に認知機能の保護に直結するとして、その重要性が高まっています。また、初期の診断における検査項目も強化されました。
- 収縮期BP 130 mm Hg未満による認知症予防の推奨
エビデンスの強度が増した結果、改訂された推奨では、軽度認知障害と認知症を予防するために、収縮期BPを130 mm Hg未満に下げるべきとされています。ジョーンズ医師は、中年の高血圧患者の収縮期BPを130 mm Hg未満に下げることで、認知症のリスクが減少することが「確実になった」と述べています。高血圧が認知機能に関わる脳領域の小血管に損傷を与えるという考えに基づき、認知症予防は、CVDリスクが低いステージ1高血圧患者であっても、早期に薬物療法を開始する根拠の一つとなっています。 - 標準検査項目への追加と原発性アルドステロン症のスクリーニング拡大
診断段階で2つの重要な検査項目が追加されました。
原発性アルドステロン症のスクリーニング拡大: この疾患は以前考えられていたよりも一般的に存在し(ステージ1高血圧の最大10%、抵抗性高血圧の最大約20%)、抵抗性高血圧や閉塞性睡眠時無呼吸症候群などの患者に対して、低カリウム血症の有無にかかわらず、血漿アルドステロン・レニン比による検査が推奨されています。重要な点として、新しいガイダンスでは、スクリーニング前に降圧薬を中止するという従来の障壁を避け、ほとんどの降圧薬を安全に継続できると明確化されました。
尿中アルブミン・クレアチニン比(UACR)の測定: すべての高血圧患者の標準検査の一部として追加されました。これは、血清クレアチニン検査よりも初期の腎臓病に対して感度が高く、早期検出により腎不全への進行リスクを減らす適切な治療を可能にします。
4.生活習慣指導の普遍化と具体的な数値目標
新しいガイドラインでは、生活習慣の推奨が高血圧の有無にかかわらずすべての成人へと対象を拡大し、具体的な数値目標が設定されています。
アルコール摂取の理想は「禁酒」
以前のガイドラインはBPが高い人に飲酒を制限するよう勧告していましたが、今回の更新では、すべての成人に対して飲酒を控えるよう助言しています。これは、少量であってもアルコール摂取により、収縮期BPと拡張期BPの両方が時間とともに上昇するためです。高血圧を持つ人、または高血圧を予防したい人にとっての理想は、アルコール摂取なし(禁酒)であると明確に示されました。
減塩とカリウム強化塩代替品の推奨
低ナトリウム食は、高血圧治療の基本として、すべての成人に対して推奨されています。具体的な目標は、ナトリウム摂取量を1日あたり2300 mg未満(理想的には1500 mg未満)に減らすことです。
また、食塩中のナトリウムレベルを下げ、カリウムレベルを上げるカリウム強化塩代替品の使用が強く支持されています。これはBPを下げるのに有用ですが、慢性腎臓病(CKD)患者には推奨されないため、薬剤師は患者指導の際にこの点に注意を払う必要があります。
体重減少の具体的目標
過体重または肥満の成人は、高血圧の有無にかかわらずBPを下げるのにより効果的であるというデータに基づき、少なくとも体重の5%以上を減らすか、BMIを少なくとも3ポイント減らすことを目標とすべきとされました。
さらに、本ガイドラインでは、GLP-1受容体作動薬(体重管理に使用される)が「BPを下げるための補助療法として効果的である可能性がある」と初めて言及されています。
総括
新しいAHA/ACCガイドラインは、高血圧管理において、「より早く、より低く」という一貫した治療哲学を示しています。これは、薬物療法と生活習慣介入の境界を早期化・普遍化し、認知症を含む長期的な予後改善を目指すものです。
薬剤師は、配合剤によるアドヒアランス向上の支援、新しいリスク評価(PREVENT)に基づく治療目標の理解、そして特に減塩指導と禁酒の重要性といった普遍化された生活習慣の推奨について、患者様へ具体的に指導する重要な役割を担います。このガイドラインは、高血圧管理における私たちの役割が、単なる調剤から、より積極的な予防医学的介入へと拡大していることを示唆していると言えるでしょう。