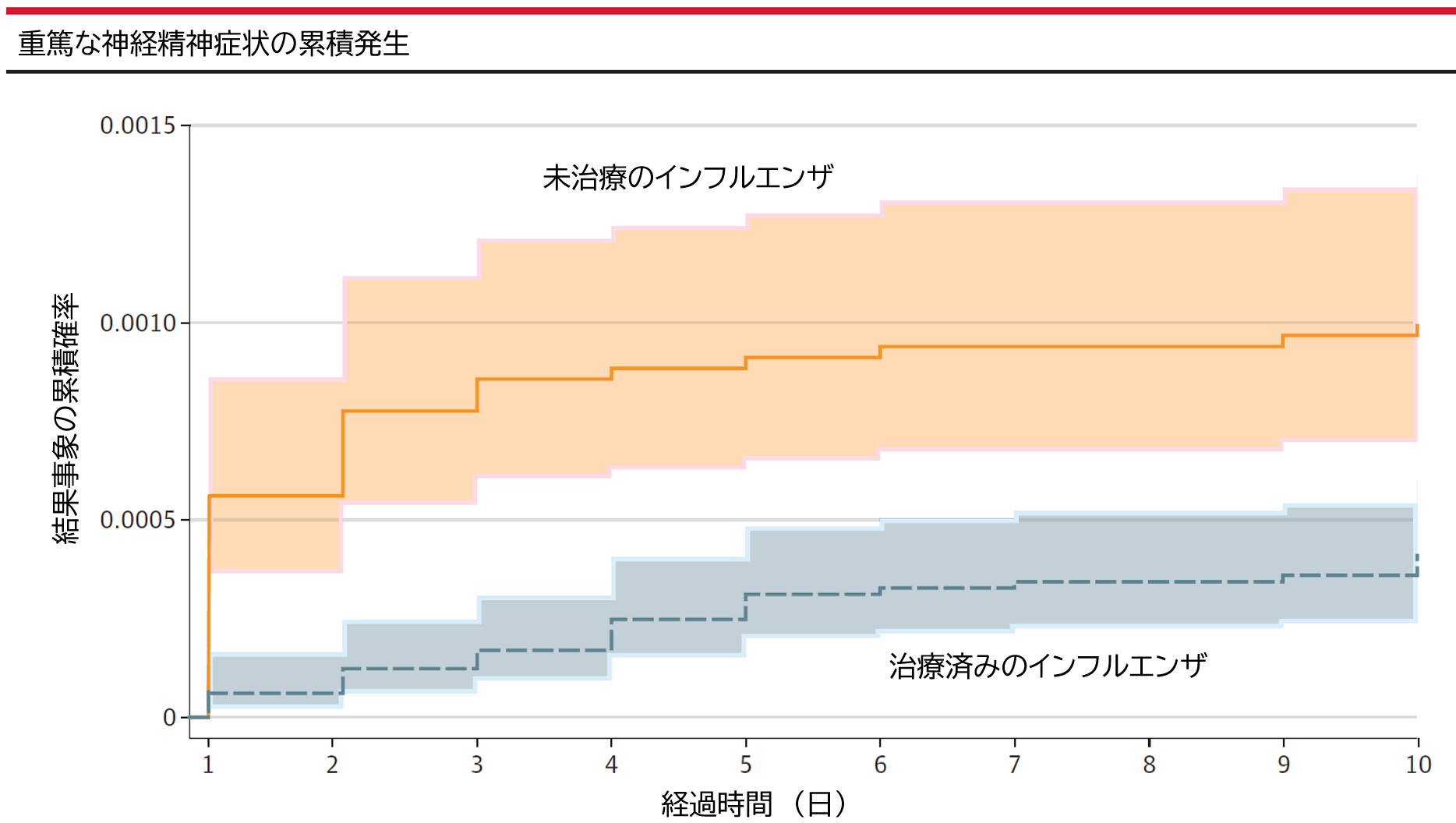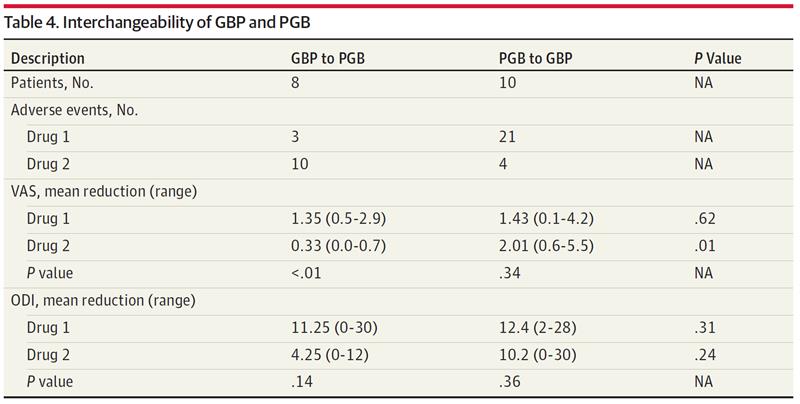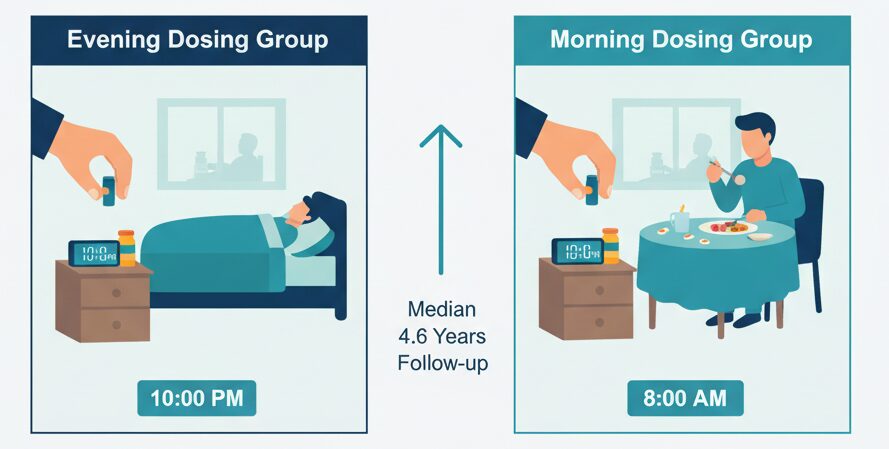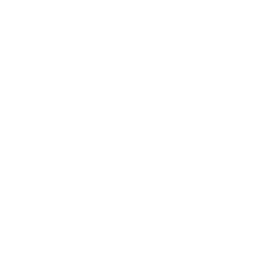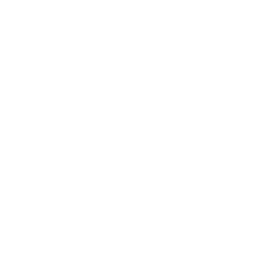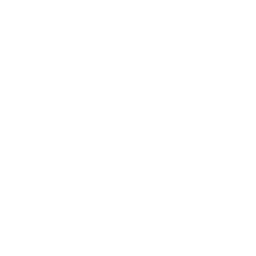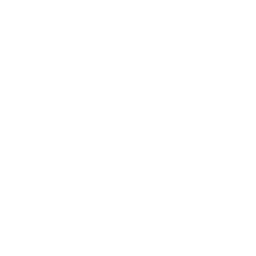薬剤師の学びとキャリアに役立つ情報サイト
メディセレメディア
新着記事
New articles

登録販売者として就職できない?難易度や正社員登用への近道を解説
登録販売者になろうと思ったときに「就職が難しいのでは」と不安を感じる方もいるかもしれません。実際には資格を活かせる環境は多く存在し、工夫次第で正社員として安定して働くことも可能です。本記事では、登録販売者の就職難易度や就職活動で意識すべき…

薬剤師国家試験 直前1ヶ月、まだ伸びる!合格を掴むための5つの逆転戦略
はじめに 薬剤師国家試験まで残り1ヶ月。この時期になると、「本当に合格できるだろうか」という不安や焦りが生じてしまうかもしれません。これまで膨大な時間を勉強に費やしてきたからこそ、プレッシャーを感じるのは当然のことです。 しかし、この直…


薬剤師の役割とは?職場ごとの仕事内容と求められるスキルを解説
薬剤師は薬を扱う専門家として、患者さまの健康を支える重要な役割を担っています。調剤や服薬指導に加え、災害支援といった社会的活動まで、幅広い場面で活躍する存在です。この記事では、薬剤師の役割を職場ごとに整理し、必要とされるスキルやキャリア形…
人気記事
Popular articles
- 1

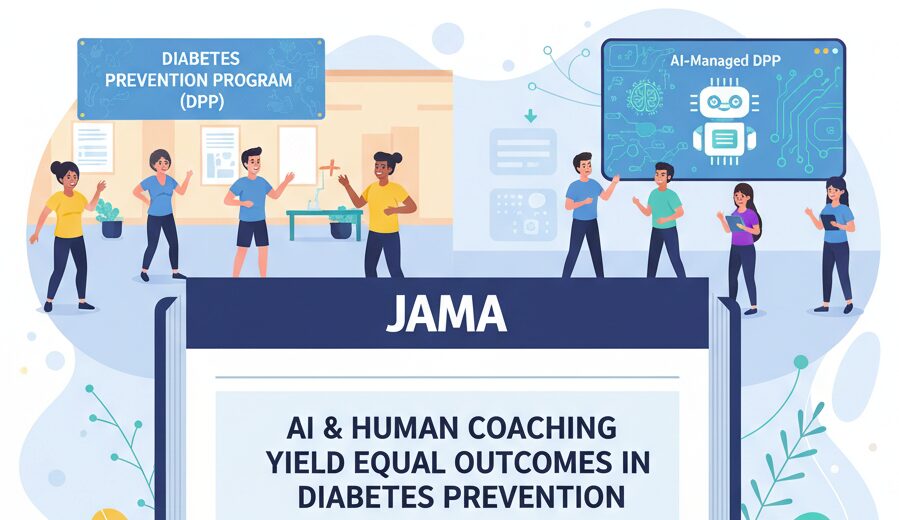
糖尿病予防プログラム(DPP)の未来—AI介入の登場と薬局の役割—
世の中、AIが社会や人の役割を変えようとしています。これは医療においても同じことが言えます。JAMAに興味深い論文が掲載されました。糖尿病予防プログラムは、人が指導してもAIが管理しても同じ結果が得られる、というものです。本論文は、米国の成人の約38%が罹患している前糖尿病に対する、エビデンスに基づいた標準的な予防策である糖尿病予防プログラム(DPP)が、プログラムの利用制限や低い参加率という重大な実施上の課題を抱えている点を取り上げています。この問題を解決するため、研究の興味(目的)人…
- 2


脳卒中後の抗血小板薬追加で出血リスクは2倍〜抗凝固薬単独療法が出血リスクを抑制する可能性を示す日本のRCT〜
- 3


「漢方専門」の薬剤師がいる?隣国・韓国の薬剤師事情、日本とこんなに違う5つの驚き
- 4

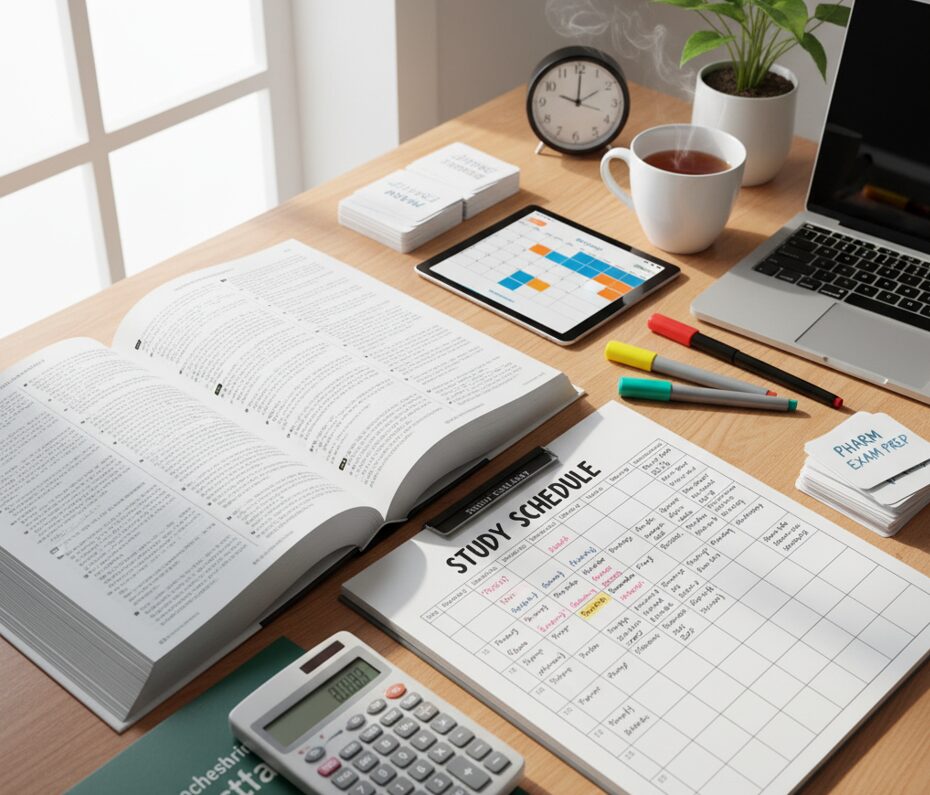
薬学部低学年に効果的な勉強方法と計画と効率的な進め方
- 5


災害時における市販薬(OTC)過剰服用問題と薬剤師の役割
- 6


妊娠中のアセトアミノフェン使用と神経発達障害リスクに関する最新の科学的知見
薬学生向けコンテンツ


登録販売者として就職できない?難易度や正社員登用への近道を解説
登録販売者になろうと思ったときに「就職が難しいのでは」と不安を感じる方もいるかもしれません。実際には資格を活かせる環境は多く存在し、工夫次第で正社員として安定して働くことも可能です。本記事では、登録販売者の就職難易度や就職活動で意識すべき点を紹介します。 この記事を読むための時間:3分 登録販売者の就職難易度 登録販売者は、資格を持っているだけで採用が保証されるわけではなく、勤務先によっては経験やスキルを重視されることがあります。とくに都市部ではライバルが多いため、就職活動に苦労するケースも少なくありません。ただし地方や人手不足の地域では、採用されやすい傾向も見られます。就職の難易度は一概に高いわけではなく、環境や準備の仕方で大きく変わるのが実情です。 登録販売者が就職できないと感じたときの対策 登録販売者が就職できないと感じたときの対策は、以下のとおりです。 パートやアルバイトから経験を積む 勉強を継続し最新の知識を身につける 就職エージェントを活用する パートやアルバイトから経験を積む 最初から正社員としての採用を狙うのが難しい場合、パートやアルバイトで経験を…

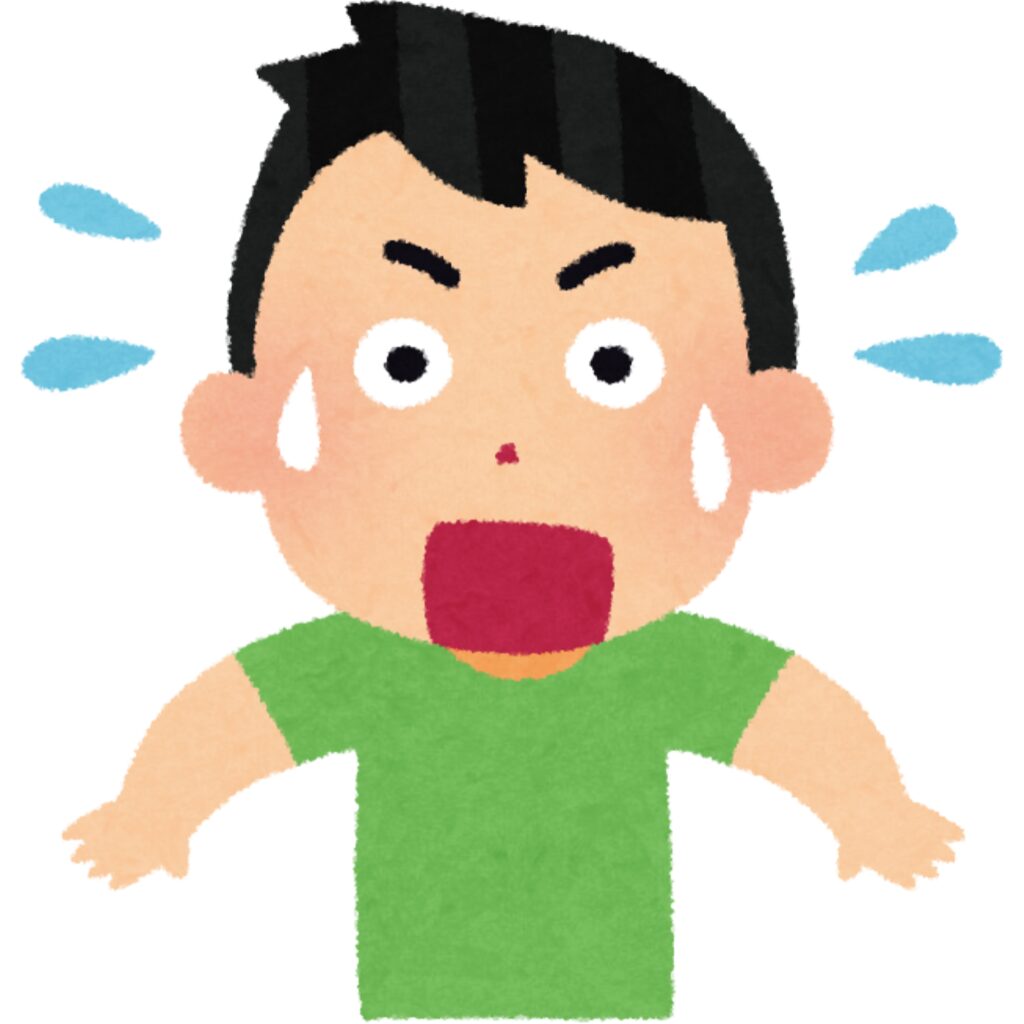
薬剤師国家試験 直前1ヶ月、まだ伸びる!合格を掴むための5つの逆転戦略
はじめに 薬剤師国家試験まで残り1ヶ月。この時期になると、「本当に合格できるだろうか」という不安や焦りが生じてしまうかもしれません。これまで膨大な時間を勉強に費やしてきたからこそ、プレッシャーを感じるのは当然のことです。 しかし、この直前期の過ごし方こそが、合否を分ける重要な鍵となります。この記事では、予備校の知見に基づき、残された1ヶ月で最大の効果を発揮するための、具体的で実践的な5つの戦略をご紹介します。不安を力に変え、合格を確実なものにするための行動を始めましょう。 ——————————————————————————– 1. 目的は「覚え直す」こと。新しい知識より反復が勝負を決める 直前期の勉強における最大の目的は、新しい知識を詰め込むことではありません。これまで学んできた膨大な知識を「覚え直す」ことです。皆さんの頭の中には、すでに合格に必要な知識が蓄積されています。しかし、人間の脳は忘れるようにできています。大切なのは、試験当日にその知識を最大限引き出せる状態にしておくことです。 この時期は、新たな参考書に手を出すのではなく、今まで使ってきた…


薬剤師の役割とは?職場ごとの仕事内容と求められるスキルを解説
薬剤師は薬を扱う専門家として、患者さまの健康を支える重要な役割を担っています。調剤や服薬指導に加え、災害支援といった社会的活動まで、幅広い場面で活躍する存在です。この記事では、薬剤師の役割を職場ごとに整理し、必要とされるスキルやキャリア形成への活かし方を解説します。 この記事を読むための時間:3分 薬剤師に求められる役割とは 薬剤師の役割は、薬を渡すだけではありません。患者さまの安全と健康を守るため、処方箋に基づく調剤や服薬指導を行い、薬の相互作用や副作用を確認します。また、医師や看護師と連携して治療を支える重要な存在であり、災害時の医薬品供給や地域住民からの健康相談など、社会全体を支える役割も担っています。 職場ごとに異なる薬剤師の役割 薬剤師は、勤務先によって求められる役割が異なります。 薬局薬剤師の役割 病院薬剤師の役割 製薬会社での薬剤師の役割 行政での薬剤師の役割 それぞれ詳しく解説します。 薬局薬剤師の役割 薬局薬剤師は地域医療の現場で、患者さまに最も近い存在として活躍しています。薬局の形態によって、さらに役割が細かく分かれます。 門前薬局 …
薬剤師向けコンテンツ

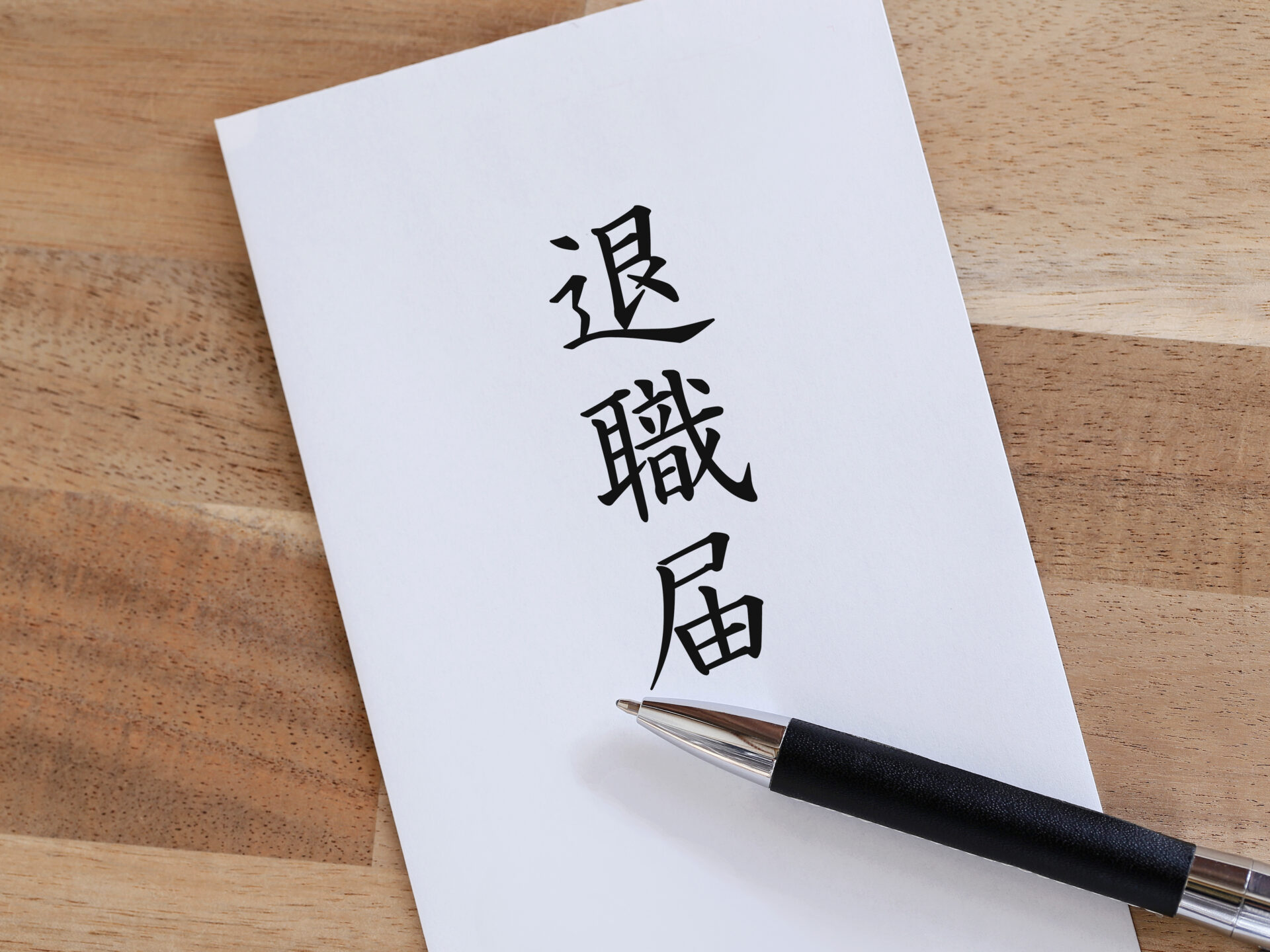
仕事を辞めたい新人薬剤師必見!対処法や早期退職のデメリットを紹介
新人薬剤師として働き始めたばかりの頃は、多くの人が不安を抱えるものです。仕事に慣れないうちは「辞めたい」と思う瞬間が出てきても不思議ではありません。本記事では、新人薬剤師が辞めたいと感じる理由や取るべき行動、早期退職のメリットとデメリットを解説します。 この記事を読むための時間:3分 新人薬剤師が「仕事を辞めたい」と思う理由 新人薬剤師が仕事を辞めたいと思う理由は、以下のとおりです。 職場に馴染めない 業務量や責任の重さに耐えきれない 職場に馴染めない 入社直後は、職場の雰囲気や人間関係に適応できず、孤立感を抱くことがあります。周囲に相談しにくい状況が続くと、不安が強まり退職を考えやすくなるものです。小さな違和感が積み重なり「ここには合わないのでは」と悩む新人も少なくありません。 業務量や責任の重さに耐えきれない 調剤や服薬指導、在庫管理など、新人でも多くの仕事を任されます。責任の大きさに押しつぶされそうになり、精神的な負担が限界に近づく場合もあるでしょう。自分の力不足を感じやすく、辞めたい気持ちにつながります。 新人薬剤師が仕事を辞めたいときにやるべきこと 新…


薬剤師の調剤ミスはなぜ起こる?主な原因と現場の防止策を解説
薬剤師の調剤業務は、患者さまの健康を守るうえで欠かせません。しかし、確認不足や環境要因によって調剤ミスが発生することがあります。ミスは患者さまの健康被害や薬局の信頼低下につながるため、原因を明らかにし防止策を徹底することが重要です。この記事では、調剤ミスの主な原因と現場で実践できる対策を解説します。 この記事を読むための時間:3分 薬剤師が起こす調剤ミスとは 薬剤師の調剤ミスとは、処方箋に沿って薬を準備・提供する過程で発生する誤りのことです。日本薬剤師会では、調剤ミスを次の3つに分類しています。 調剤事故 薬剤師の過失に関わらず、患者さまに健康被害が発生したもの 調剤過誤 調剤事故のうち、薬剤師の過失によって発生したもの ヒヤリ・ハット事例 健康被害が出なくても、ヒヤリとするミスが起きた場合 (インシデント事例とも呼ばれる) 参照:新任薬剤師のための調剤事故防止テキスト(第二版)|日本薬剤師会 調剤事故は医療事故の一種であり、「薬の種類や量を間違える」「服用方法を誤って伝える」といったケースは重大な問題につながります。 薬剤師の調剤ミスが起こる主な原因 薬剤師の調剤ミス…


新人薬剤師必見!就職してからやるべきこと7選を徹底解説
薬剤師として就職すると、実務や人間関係、勉強の両立など、多くの新しい環境に向き合わなければなりません。とくに、新人の時期は覚えることが多く、不安や戸惑いを抱きやすいものです。そこで本記事では、新人薬剤師が就職後に取り組むべきことを、7つの視点から解説します。 この記事を読むための時間:3分 新人薬剤師が就職後にやるべきこと7選 新人薬剤師が就職後にやるべきことは、以下のとおりです。 職場のルールやマナーを身につける 先輩薬剤師から積極的に学ぶ 患者とのコミュニケーションに力を入れる 調剤や服薬指導の基本を確実に身につける チーム医療での役割を理解する 最新の知識をアップデートする ライフワークバランスを意識する 職場のルールやマナーを身につける 新人薬剤師にとってまず大切なのは、職場の基本的なルールやマナーを理解することです。挨拶や報連相の徹底はもちろん、服装や清潔感も信頼に直結します。社会人としての基本を守る姿勢が、同僚や患者との円滑な関係作りにつながります。 先輩薬剤師から積極的に学ぶ 実務経験が浅い時期は、先輩薬剤師の行動から学ぶ姿勢が大切です。調剤や…
薬剤師開業向けコンテンツ


【速報】薬局1店舗あたり最大23万円支給へ|令和7年度補正予算の「実利」と「条件」を徹底解説
はじめに 2025年11月28日、政府は総合経済対策の裏付けとなる令和7年度補正予算案を閣議決定しました。今回の発表で、薬局経営者にとって最もインパクトがあるのは、抽象的な支援策ではなく、明確な金額が示された「医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援」です。 総額5,341億円規模の支援パッケージの中で、薬局に対して具体的にどのような現金給付が予定されているのか。本記事では、メディセレメディア読者の皆様に向け、発表されたばかりの一次情報に基づき、支給額の区分と実務上の注意点を速報します。 1. 【事実認定】支給額は「法人規模」で決まる 今回の支援金は、一律ではありません。法人の規模(店舗数)に応じた傾斜配分が採用されています。 厚生労働省の発表資料に基づく支給額の内訳は以下の通りです。 薬局1施設あたりの支援額(予定) 支援金は「賃上げ支援分」と「物価高騰対応分」の合算となります。 ① 5店舗以下の法人 賃上げ支援分:14.5万円 物価高騰分 : 8.5万円 合計:23.0万円 ② 6店舗~19店舗の法人 賃上げ支援分:10.5万円 物価高騰分 : 7.5万円 合計:18.0万円 ③ 20店…


【経営者必読】2026年診療報酬改定の「標的」はどこか?厚労省資料から読み解く生存戦略
2026年(令和8年)の診療報酬改定に向けた議論が、いよいよ本格化しています。 薬局経営者にとって、改定は単なる「点数の変更」ではありません。それは国の医療政策が、どのタイプの薬局を「残し」、どのタイプの薬局を「淘汰」しようとしているかを示す、明確なメッセージ(生存要件)です。 本記事では、現在(2025年11月時点)厚生労働省の中医協(中央社会保険医療協議会)等で議論されている確実な一次情報を基に、2026年改定の重要論点と、今すぐ着手すべき経営防衛策を解説します。 1. 【事実認定】「薬剤師偏在」問題が招く調剤基本料の厳格化 2025年9月以降、中医協で最も熱を帯びている議論の一つが「薬剤師の偏在」です。 厚労省の提示した事実 厚労省の資料では、「薬局薬剤師は増加傾向にあるが、病院薬剤師は不足している」というデータが明確に示されています。これに対し、財務省や支払側(健保連等)からは、「薬局への評価(報酬)が手厚すぎるため、人材が偏っているのではないか」という厳しい指摘がなされています。 経営への影響とリスク この議論の着地点は、「薬局薬剤師の労働対効果のシビアな査定」です。 単に処方…


薬剤師のキャリアプランとは?代表的なパターンと実現方法を解説
薬剤師として働くうえで、キャリアプランを考えることは、将来の安定や成長につながります。薬局や病院、製薬企業など進路の選択肢は幅広く、それぞれに必要なスキルや資格も異なります。自分に合った道を選べば、希望する働き方を実現しやすくなるでしょう。この記事では、薬剤師の代表的なキャリアプランと、実現方法について解説します。 この記事を読むための時間:3分 薬剤師のキャリアプランの重要性とは 薬剤師にとってキャリアプランは、将来の安定や成長に欠かせません。薬局や病院、企業など進路が幅広いため、方向性を決めないまま働くと、スキルを活かす機会を逃してしまいます。早めに目標を定めれば、必要な資格や経験を計画的に積み重ねられ、面接でのキャリアビジョンも明確に伝えられるでしょう。 薬剤師のキャリアプランの具体例 薬剤師のキャリアプランは、以下に大別できます。 独立を目指せる管理職のキャリア 専門資格を活かしたキャリア それぞれの違いを詳しく解説します。 独立を目指せる管理職のキャリア 管理薬剤師やエリアマネージャーなど、組織の運営に携わるポジションを目指すのは、薬剤師の代表的なキャ…
カテゴリー一覧
Category