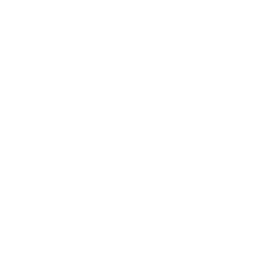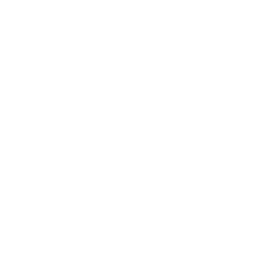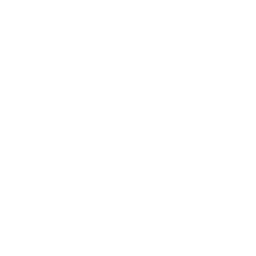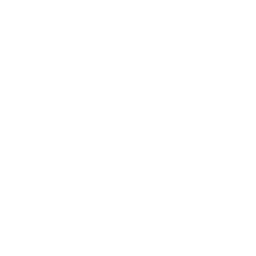糖尿病予防プログラム(DPP)の未来—AI介入の登場と薬局の役割—
世の中、AIが社会や人の役割を変えようとしています。これは医療においても同じことが言えます。JAMAに興味深い論文が掲載されました。糖尿病予防プログラムは、人が指導してもAIが管理しても同じ結果が得られる、というものです。
本論文は、米国の成人の約38%が罹患している前糖尿病に対する、エビデンスに基づいた標準的な予防策である糖尿病予防プログラム(DPP)が、プログラムの利用制限や低い参加率という重大な実施上の課題を抱えている点を取り上げています。この問題を解決するため、研究の興味(目的)人間コーチ主導のDPPと比較して、体重減少、HbA1c改善、身体活動といった複合的な健康アウトカムを達成する上で非劣性であるかどうかを検証することです。
本研究は、AI主導型DPPが人間の介入なしに有効性を維持できるか、そしてその拡張性(スケーラビリティ)実行可能な代替手段となり得るかを評価する点で重要です。
JAMA Original Investigation
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2840703
1.前糖尿病の蔓延と従来のDPPが抱える「アクセスの壁」
前糖尿病(prediabetes)は、現在、米国の成人のおよそ38%に影響を与えており、その有病率は世界的に増加しています。前糖尿病の状態にある成人の約20%から50%は5年以内に糖尿病へと進行すると予測されており、効果的な予防戦略の実施は公衆衛生上の喫緊の課題です。
糖尿病リスクを58%低減するという結果が示されたDPP(糖尿病予防プログラム)のライフスタイル介入は、この予防のための標準的な方法(criterion standard)とされています。しかしながら、その実施には大きな障壁が存在します。プログラムの利用可能性の制限や、医療機関から紹介されたにもかかわらず実際の参加率が低いこと(約35%)が問題となっています。DPPの介入がガイドラインで推奨されているにもかかわらず、実際にプログラムに参加している米国の前糖尿病患者はわずか3%にとどまっています。
従来のDPPは対面でのセッションが中心でしたが、COVID-19パンデミック以降は遠隔でのグループビデオ会議が主流となりました。このデジタル化は利用を促進するものの、さらに多くの人々、特に構造的な介入を現在受けていない人々に届くためには、スケーラビリティ(拡張性)を高めるアプローチが必要です。
2. AI主導型DPP、人間主導型に対し「非劣性」を証明
こうした背景のもと、完全に自動化されたAI(人工知能)を活用したライフスタイル介入プログラムが、従来の人間コーチによる指導と比較して、有効性が劣らないか(非劣性)を検証するランダム化比較試験(RCT)が実施されました。
本研究では、前糖尿病かつ過体重または肥満の成人368名を対象に、AI主導型DPPと人間コーチ主導型DPPの有効性が比較されました。主要評価項目は、12ヶ月時点での体重減少、身体活動、HbA1cの維持・改善からなる複合アウトカムでした。
その結果、複合アウトカムの達成率は以下の通りでした。
- AI主導型DPPグループ: 31.7% (183名中58名)
- 人間主導型DPPグループ: 31.9% (185名中59名)
両グループのリスク差はわずか-0.2%であり、非劣性基準として事前に設定されたマージン(-15%)を満たしたため、AI主導型DPPへの紹介は、人間主導型DPPへの紹介に対して非劣性であると結論付けられました。
つまり、プログラムの有効性という点で、AIは人間のコーチングに匹敵することが示されたのです。
3.AI主導型の優位性—開始率と継続率の向上
主要な有効性のアウトカムは同等でしたが、本研究で特筆すべきは、プログラムへのエンゲージメント(関与)に関する結果です。
AI主導型DPPは、人間主導型DPPと比較して、以下の点で統計的に高い数値を示しました。
AI主導型 DPP プログラム開始率/プログラム完了率 93.4%/63.9%
人間主導型 DPP プログラム開始率/プログラム完了率 82.7%/50.3%
AI主導型DPPは、モバイルアプリとBluetooth対応の体重計を通じて、強化学習アルゴリズムによって個別化されたプッシュ通知(例:運動や栄養に関するジャストインタイムのヒント)を非同期かつ低タッチで提供しました。この非同期性、オンデマンド性、利便性の高さが、参加の障壁を下げ、プログラムの開始と完了を促進したと考えられます。
研究者は、AI主導型DPPの価値は有効性の「優越性」ではなく、「スケーラビリティ(拡張性)」にあることを示唆しています。AIベースのアプローチは、人的コーチングの必要性を減らし、より多くの人々に介入を届ける実行可能な代替手段となり得るのです。
4.薬局薬剤師の今後—AIデバイスを「介在」させる役割
AI主導型DPPというスケーラブルなツールが登場した今、地域に密着した薬局の薬剤師は、このデジタルイノベーションをどのように活用すべきでしょうか。
介入の「ゲートキーパー」となる
薬剤師は、前糖尿病患者に対して、どのDPP形態が最も適しているかを判断する「ゲートキーパー」としての役割を担うべきです。
AI主導型DPPを推奨すべき対象: 多忙でスケジュールの柔軟性を求める患者、または地理的な制約や移動手段の制約がある患者に対しては、高い開始率と完了率が期待できるAI主導型DPPを積極的に推奨できます。
人間主導型DPPを推奨すべき対象: デジタルリテラシーに不安がある患者、対面での人間的な交流やグループサポートを強く好む患者、あるいはAIの探索的サブグループ解析で有効性が低い可能性が示唆された一部の層(高齢者や低BMI層)に対しては、人間コーチ主導型DPPを強く推奨し、介入の「ギャップ」を埋めます。
複合的なアウトカムの評価と連携
AI-DPPの有効性が、体重減少、身体活動、HbA1cの維持・改善という複合アウトカムに基づいて評価されている点を踏まえ、薬剤師は、処方薬の提供だけでなく、患者のAIアプリの使用状況や、自己報告されるライフスタイル改善の努力を評価し、医師や他の医療専門職、またはAIプログラム自体にフィードバックする役割を担うべきです。AIによる介入は、患者が自己主導的なエンゲージメントを継続することに依存するため、定期的な薬局訪問の際に、その継続を励ます声かけは、有効性の維持に貢献するでしょう。
AI主導型DPPの登場は、薬剤師が患者の生活習慣介入をよりスケーラブルかつ個別化された方法で支援するための強力なツールを提供します。薬剤師は、この新しい技術を地域医療に組み込むことで、前糖尿病患者の増加に対する包括的な予防対策の実現に貢献できるのです。
デジタルリテラシーとエンゲージメントの支援
AI主導型DPPはプログラムの完了率を高めましたが、導入時にはデジタルデバイス(アプリやBluetooth体重計)のセットアップが必要です。薬剤師は、服薬指導時にこれらのAIデバイスの使用方法やデータの読み取り方について簡単に指導を行うことで、患者の初期のデジタルバリアを低減し、プログラム開始率のさらなる向上をサポートできます。薬局は、単に薬を受け取る場所ではなく、健康行動変容を支援するデジタルデバイスのサポートセンターとなることが期待されます。