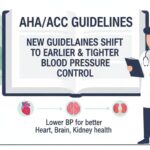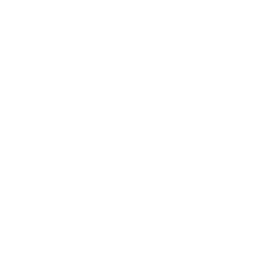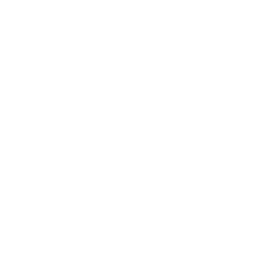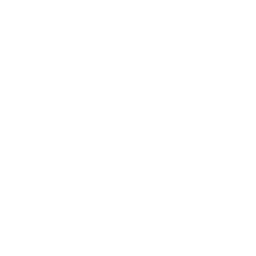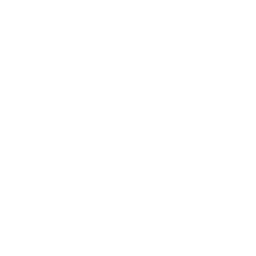薬学部で効果的な勉強法は?進級できる人の特徴もあわせて解説
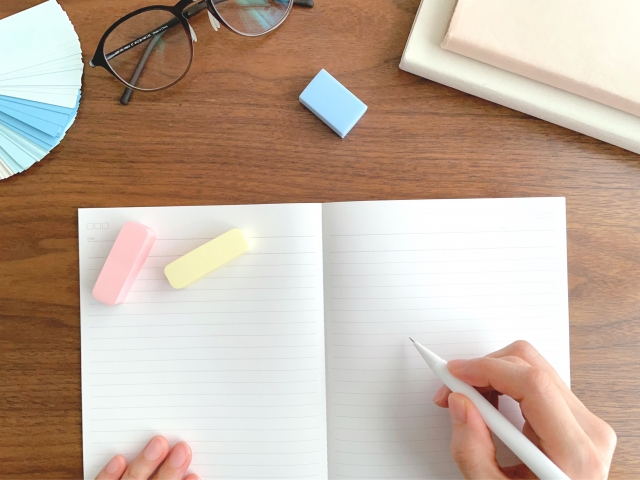
薬学部は6年間にわたる長期の学習が求められ、学年ごとに習得すべき知識やスキルも異なります。そのため、学年に合った勉強法を実践することが大切です。しかし、どのような方法で勉強すれば良いのかわからず、悩まれる方もいるでしょう。この記事では、薬学部で効果的な勉強法について解説します。進級できる人の特徴もあわせて紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むための時間:3分
【学年別】薬学部で効果的な勉強法
ここからは、以下の学年別に薬学部で効果的な勉強法を解説します。
- 1年生
- 2年生
- 3年生
- 4年生
- 5年生
- 6年生
1年生
薬学部1年生では、薬理や病態生理よりも生物学・化学などの基礎科目を学びます。この時期に理解重視の勉強習慣を身につけ、授業は欠席せず復習をその日に行いましょう。定期試験対策は範囲公開時から計画的に進め、過去問分析も忘れずに行うことが進級の鍵です。
2年生
2年生では免疫学・微生物学・薬理学などの専門科目が始まり、1年生での基礎が理解の鍵となります。暗記だけに頼らず「理解して覚える」勉強を継続し、薬理学は語呂なども活用しましょう。授業出席と定期試験対策は1ヶ月前から計画的に行い、進級試験の有無も確認しておくことが大切です。
3年生
3年生では基礎科目が減り、薬理学や病態生理学に加え、製剤学や薬物動態学も学びます。薬物動態学は計算が多く苦手な人は注意が必要です。進級対策としては、授業への出席と早めの定期試験対策、過去問分析を欠かさず行うことが重要です。
4年生
4年生では専門科目を学びつつ、5年生の実務実習に進むために薬学共用試験に合格する必要があります。薬学共用試験はCBT(筆記)とOSCE(実技)で構成され、知識・技能・態度の基準を評価します。大学の定期試験に合格しても、CBTに合格しなければ進級や実務実習はできません。
5年生
5年生では病院・薬局で約5ヶ月の実務実習を行い、修了することで単位が取得できます。実務実習は国家試験対策にも重要です。しかし、座学の習慣が途切れやすいため、実習時間外に必須問題などを自主学習し、6年生進級テストの対策も忘れずに行いましょう。
6年生
6年生は国家試験だけでなく、卒業論文・卒業試験・就職活動など多忙な学年です。卒業試験は国家試験より難しく、大学の合格率維持のために難易度が高めに設定されています。過去2~3年分の国家試験・卒業試験の過去問を9月までに解き、教授独自の出題にも備えておくことが重要です。
進級できる人の特徴
進級できる人の特徴は、以下の4つです。
- 大学の講義を集中して聞いている
- わからないことは確認する
- 早めに試験勉強を始めている
- 一緒に勉強する仲間がいる
大学の講義を集中して聞いている
進級できる学生は、単にノートを取るだけでなく、教授の説明・板書・資料のポイントを意識して集中し、疑問点をその場で整理することで理解を深めます。講義を効率よく聞くことで、後から復習する時間を大幅に短縮可能です。
わからないことは確認する
薬学は専門知識が多く、理解が不十分なままにしておくと、後の学習や試験でつまずきやすくなります。進級できる学生は、授業の疑問点を放置しません。教員・先輩・友達に質問して積極的に確認します。その場でわからない内容を解消することで理解が確実になり、応用問題にも対応できる力が養われます。
早めに試験勉強を始めている
試験直前に慌てて勉強するのではなく、余裕を持って準備することが大切です。進級できる学生は、試験日から逆算して計画的に学習を進め、苦手分野の克服や過去問演習に十分な時間を確保しています。早めに準備することで、焦りやストレスも減らせるでしょう。
一緒に勉強する仲間がいる
1人で勉強するよりも、仲間と協力して学ぶことで理解が深まる場合があります。進級できる学生は、問題を出し合ったり教え合ったりして知識を定着させます。また、勉強仲間がいるとモチベーションが維持でき、学習習慣の継続にもつながりやすいです。
学年別のポイントを押さえて効率的に知識を身につけよう!
薬学部での勉強は、学年ごとに必要なスキルや学習内容が変わります。1~2年生は基礎力を固め、3~4年生は専門知識の理解を深め、5~6年生は実務力と国家試験対策を中心に学習することが効率的です。学年に合った勉強法を意識し、計画的に学習を積み重ねましょう。