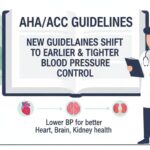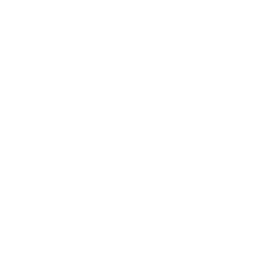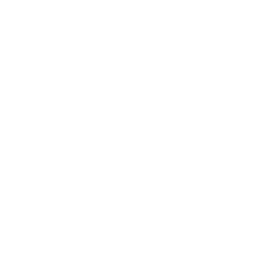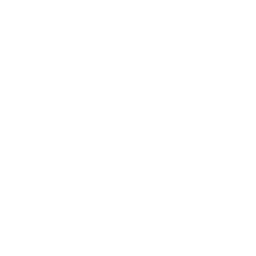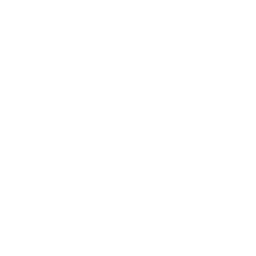薬学部におけるCBT試験とは?出題範囲や効果的な対策を解説

6年制の薬学部または薬科大学の4年次には、「CBT試験」が行われます。CBT試験は、5年次に行われる実務実習に参加するための非常に重要な試験であり、不安に感じる学生も少なくないでしょう。本記事では、CBT試験の概要と具体的な対策について解説します。これからCBT試験を控えている学生の方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を読むための時間:3分
薬学部の共用試験「CBT」とは
薬学部における「CBT」は、薬学共用試験の1つとして位置付けられています。薬学共用試験は全国の薬科大学・薬学部が共通で利用する評価試験のことで、大学間の格差をなくして薬学生のレベルを一定水準に保つために行われるものです。薬学共用試験には「CBT」のほかに「OSCE」という客観的臨床能力試験もあります。ここでは、CBT試験について以下の4つの観点から詳しく解説します。
- CBT試験の概要
- CBT試験の目的
- CBT試験の出題範囲
- CBT試験の合格率と難易度
CBT試験の概要
薬学部で行われるCBT(Computer Based Testing)は、薬学の基礎知識を評価するためのコンピューター形式の試験です。大学ごとのスケジュールに合わせて試験日が設定され、大学のPCを用いて行われます。出題形式は、5つの選択肢から正しいものを選ぶ多肢選択式です。
CBT試験の大きな特徴は、受験生ごとに異なる問題が出題されることです。ただし、公平性を保つため、体験受験や過去の結果から算出された各問題の期待正答率をもとに、難易度が同じになるように調整されます。
試験終了後の結果は1週間以内に薬学共用試験センターから各大学へ送られ、各大学がその情報をもとに合否を判定し、学生へ通知します。試験に落ちた場合は、本試験と同じ年度内に1度だけ再試験を受けられますが、再度すべてのゾーンを受け直さなければなりません。
受験料は24,000円で、各大学で徴収してまとめてセンターに支払われます。再試験を受ける場合は、12,000円必要です。また、病気等のやむを得ない理由で試験が受けられなかった場合は、追試験の対象となります。再試験と同じ日程で実施されますが、追試験の追・再試験はありません。
CBT試験の目的
CBT試験を行う目的は、5年次に行われる実務実習を行うために必要な知識や態度が一定の基準に達しているかを評価することです。5年次には病院と薬局で実務実習を行いますが、本来は薬剤師資格をもたない薬学生は調剤行為ができません。そのため、実習に参加するには、患者の安全を守るために最低限の知識や態度を身につけていることを証明する必要があります。
CBT試験はその役割を担っており、試験に合格することで安心して実務実習に取り組めるだけでなく、患者や指導薬剤師からも「適切に教育を受けた学生」として認められるのです。
CBT試験の出題範囲
CBT試験の出題範囲は、3つのゾーンに分かれており、合計310問が出題されます。
|
ゾーン |
出題内容 |
問題数 |
ゾーンごとの問題数 |
|
ゾーン1 |
|
30題 35題 35題 |
合計100題 |
|
ゾーン2 |
|
60題 15題 35題 |
合計110題 |
|
ゾーン3 |
|
10題 20題 40題 30題 |
合計100題 |
CBT試験の合格率と難易度
CBT試験の合格率は96%程度と高い水準にあります。過去5年間の合格率は以下のとおりです。
|
2024年度 |
95.2% |
|
2023年度 |
95.3% |
|
2022年度 |
95.8% |
|
2021年度 |
95.8% |
|
2020年度 |
96.4% |
CBT試験の問題は、各分野で取り扱われる重要なキーワードや項目に関する基本的知識を問う内容です。4年次までに学んだ知識を充分に身につけていれば、特別な対策をしなくても正答率70~80%程度が取れるように作られています。ただし、出題範囲が広いため、油断は禁物です。
参考:出題範囲 / 問題数 / 合格基準|薬学共用試験センター
参考:薬学共用試験の実施結果|薬学共用試験センター
薬学共用試験「CBT」の対策

CBT試験の合格率は高く、出題内容も基本的な問題が多いため油断してしまいがちですが、範囲が広いため余裕をもって対策していくことが大切です。ここでは、CBT試験に向けた対策を3つ紹介します。
- 試験勉強のスケジュールを立てる
- 教科書や参考書を活用する
- 体験受験を利用して試験の形式に慣れる
試験勉強のスケジュールを立てる
CBT試験対策で重要なのは、計画的に学習することです。出題範囲が広いため、直前の詰め込みでは対応できません。4年次の春頃から対策を始めると、試験日まで余裕をもって進められます。年間スケジュール例とゾーンごとの勉強法を紹介するので、参考にしてみてください。
年間スケジュール例
4年次の春から試験対策を始めた場合のスケジュール例を紹介します。
|
時期 |
勉強範囲 |
ポイント |
|
4月~5月 |
ゾーン1 |
参考書や教科書で復習し、苦手科目を洗い出す。 |
|
6月~8月 |
ゾーン2 |
7月~9月に実施される体験受験を利用する。問題集を解き、出題形式に慣れる。 |
|
9月~10月 |
ゾーン3 |
過去問題の繰り返しや模擬試験の復習で弱点を補強する。 |
|
11月~試験直前 |
ゾーン1~3 |
暗記項目を確認し、問題を繰り返し解いて定着させる。忘れている項目があれば、インプットとアウトプットを繰り返す。 |
段階的に学習を進めることで、広い範囲の知識も着実に身につけられるでしょう。
ゾーンごとの勉強法
ゾーン1は薬学の基礎項目で、1、2年次に学んでいるものがほとんどです。基礎的な内容ではありますが、4年次では忘れているケースも多いため、早めに対策することが大切です。
ゾーン2の内容のほとんどは3年次以降に学ぶものなので、ゾーン1に比べると覚え直す量は少なくなります。その中でも「医療薬学」はCBT試験全体の中で最も多い出題数を占めています。実務でも役立つ内容で構成されているため、5年次の実務実習で生かせるように重点的に取り組みましょう。
ゾーン3は比較的基本的な内容が中心で得点しやすいため、確実に得点できるよう対策を行うことが大切です。ゾーン2とゾーン3については、普段の授業内容をしっかりと理解し、試験直前には集中的に復習しましょう。このように、ゾーンごとの特徴を押さえ、計画的に学習することが安定した得点を取るポイントです。
教科書や参考書を活用する
CBT試験の学習は、教科書や参考書を活用しましょう。次のような流れを繰り返しながら学習することがおすすめです。
- 教科書で基本的な内容を確認する
- 参考書で知識を整理する
- 問題集を解く
問題集で分からなかった問題や間違えたところは教科書や参考書で確認するなど、分からない問題を確実になくしていくのがポイントです。
体験受験を利用して試験の形式に慣れる
CBT試験には、その年の7月から9月に利用できる体験受験が用意されています。体験受験の費用は2,000円で、本試験と同じ形式、問題数で行われます。本番と同じ環境で受けられるため、大学側も模擬試験として活用可能です。
さらに、分野ごとの採点結果が返却されるので、自分の苦手項目を確認できます。点数が伸びない分野を重点的に復習することで、効率的に得点アップに向けた準備が進められるでしょう。
計画的に学習を進めましょう
薬学部のCBT試験は出題内容が広範囲にわたるため、不安に感じる学生も少なくありません。合格するためには、早めに学習を始め、計画的に進めることが重要です。スケジュールを立てて段階的に学習を進め、教科書や参考書、体験受験を利用しながら試験に臨みましょう。