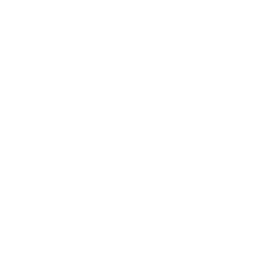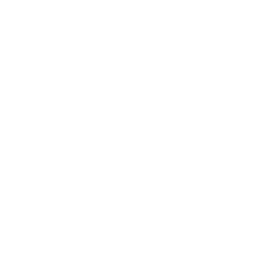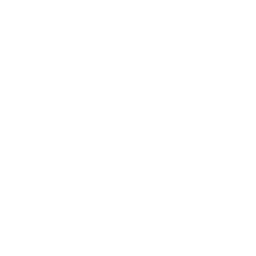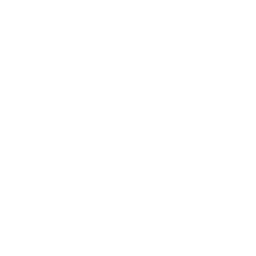2025年ESC年次学会で示された心血管領域の主要知見
2025年欧州心臓病学会(ESC)年次学会では、心血管領域における最新の臨床エビデンスが数多く報告されました。JAMA Medical Newsにその内容が紹介されています。ここでは、薬剤師として日常診療や患者支援に活かすべき重要ポイントを、以下の5つのテーマに沿って概説します。
JAMA Medical News
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2839210
1.GLP-1受容体作動薬によるHFpEF合併例の心血管イベント抑制効果
2型糖尿病および肥満を合併する左室駆出率保持型心不全(HFpEF)患者を対象に、GLP-1受容体作動薬セマグルチドおよびGIP/GLP-1作動薬チルゼパチドの有効性を検討したメタアナリシスが注目されました。この解析は58,000例を対象に複数のランダム化比較試験のデータを統合し、対照薬としてシタグリプチンを用いて心不全による入院または全死亡リスクを比較したものです。その結果、セマグルチドまたはチルゼパチドを投与された患者群では、対照群に比べて心不全関連イベントのリスクが有意に低下することが示されました。両薬剤間には有意差が認められませんでしたが、体重減少効果に優れるとされるチルゼパチドで差がなかった点は、研究者にとって意外な所見とされています。この知見は、HFpEFかつ糖尿病・肥満を合併する患者において、GLP-1受容体作動薬が体重管理のみならず心血管予後の改善にも寄与し得ることを裏付けるものです。薬剤師は、処方提案や服薬指導において、体重変化だけでなく心血管リスク低減の観点を強調することが求められます。
2.心筋梗塞後のβ遮断薬使用に関するエビデンスの更新
心筋梗塞後のβ遮断薬は、長年にわたり標準治療として位置づけられてきましたが、その根拠は現代的な血行再建術が普及する前の研究に基づくものであり、全ての患者に投与が必要かどうかについては議論が続いています。ESCでは、この問題に関する二つの対照的な研究結果が発表されました。一つ目のBETAMI-DANBLOCK試験(デンマーク・ノルウェー、5,500例)では、β遮断薬投与群において死亡または主要心血管イベント(MACE)が15%有意に減少することが示され、β遮断薬の有用性が支持されました。一方、スペインで実施されたREBOOT試験(4,243例)では、β遮断薬投与の有無で死亡、再梗塞、心不全による入院といった主要評価項目に有意な差は認められませんでした。さらに、同時に発表されたメタアナリシスでは、駆出率が軽度低下(41〜49%)した患者ではβ遮断薬の有益性が確認されたものの、駆出率が50%以上で他の適応(狭心症や不整脈など)を持たない症例では、β遮断薬を必ずしも投与する必要がない可能性が示唆されています。薬剤師は、患者の駆出率や併存症を考慮した多職種連携の中で、β遮断薬の継続や中止に関する判断を支援する役割を担うことが重要です。
3.冠動脈疾患二次予防におけるクロピドグレル単剤療法の優位性
冠動脈疾患患者の二次予防における抗血小板療法については、アスピリンとクロピドグレルのどちらを長期単剤療法として用いるべきかが議論されてきました。ESCで発表されたメタアナリシスでは、7件のランダム化比較試験、約29,000例の患者データを解析した結果、5年間の追跡においてクロピドグレル単剤療法を受けた患者は、アスピリン単剤療法を受けた患者に比べて主要心血管イベント(MACE)の発生率が14%有意に低いことが示されました。一方で、死亡率や大出血リスクについては両群間に有意な差は認められませんでした。これらの結果は、クロピドグレルがアスピリンよりも優れた選択肢であることを示し、かつ出血リスクを増加させない点で臨床的意義が大きいといえます。クロピドグレルはジェネリック医薬品として広く利用可能であることから、今後のガイドライン改訂において、アスピリンに代わる第一選択薬としての位置づけが強化される可能性があります。薬剤師は、医師がアスピリンからクロピドグレルへの切り替えを検討する背景を理解し、患者への十分な説明と服薬支援を行う必要があります。
4.帯状疱疹ワクチンと心血管リスク低減の可能性
帯状疱疹ワクチンの心血管疾患リスクに対する保護効果が、大規模な解析によって初めて示されました。ESCで発表されたシステマティックレビューおよびメタアナリシスは、19件以上の研究を対象としており、帯状疱疹ワクチンを接種した患者では、心筋梗塞および脳卒中の発症リスクが統計的に有意に低下することが明らかになりました。この関連性の正確な機序は未解明ですが、感染症に伴う炎症反応が心血管イベントの引き金となることを、ワクチン接種が回避している可能性が示唆されています。薬剤師としては、心血管リスクの高い高齢患者などに対し、帯状疱疹ワクチンの接種を推奨する意義を説明することで、患者の行動変容を促すことが心血管予防の観点からも有用です。
5.メンタルヘルスと心血管疾患に関するESCコンセンサス声明
ESCは今回初めて、メンタルヘルスと心血管疾患の双方向的な関係について公式なコンセンサス声明を発表しました。現代社会における精神的ストレスや不調は、心血管疾患の重要なリスク因子であると同時に、心血管疾患を抱える患者自身も精神的不調に陥りやすいことが知られており、両者を併発する患者は長期予後が最も不良であることが報告されています。声明では、心理的リスク因子を心血管リスク評価に組み込み、心血管ケアの中にメンタルヘルスのスクリーニングとサポートを常態化すること、さらにメンタルヘルス治療を受けている患者には定期的な心血管リスク評価を行うことが推奨されています。エビデンスに基づくガイドラインというより専門家の合意として発表された本声明は、臨床現場における意識向上と統合的ケアの必要性を訴えるものであり、薬剤師もチーム医療の一員として、心理的側面に配慮しながら服薬アドヒアランスの向上や生活習慣改善の支援を行う姿勢が求められます。
まとめ
025年ESC学会で示されたこれらの知見は、薬物治療戦略の再評価とともに、心血管リスク管理を包括的かつ個別化する重要性を浮き彫りにしました。薬剤師はこれらの最新エビデンスを理解し、処方提案、患者指導、そしてチーム医療への貢献に積極的に反映させることが期待されます。