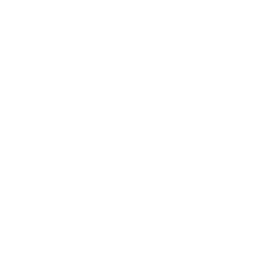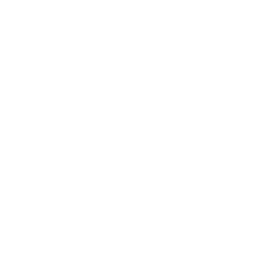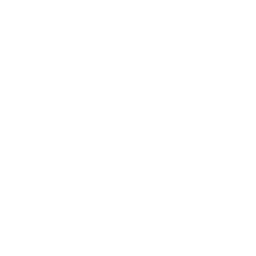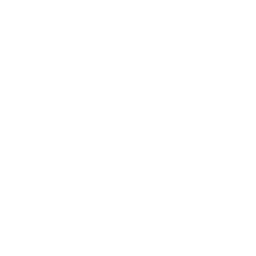日本の薬局が海外資本に狙われる!「神薬」目当ての買収と横行する違法行為の実態
最近、街の薬局が外国人経営者に変わっていることがあることにお気づきでしょうか?単なるビジネスの国際化と見ることもできますが、その裏では日本の医療制度の根幹を揺るがしかねない深刻なトラブルが多発しています。今回は、在日外国人による日本の薬局買収の背景と、実際に起きている問題について深掘りします。
なぜ日本の薬局が買収されるのか?背景にある3つの理由
日本の薬局が外国人にとって魅力的な投資対象となっているのには、いくつかの理由があります。
1. 日本の医薬品「神薬」への絶大な人気
例えば、中国では、日本の市販薬が「神薬」と呼ばれ、その品質の高さから絶大な人気を誇っています。特に、パブロン、イブ(EVE)、ロキソニン、サロンパス、ツムラの漢方シリーズなどは非常に人気が高い商品です。中国のSNSでは「日本に行ったら購入すべき神薬」といったリストが拡散され、多くの観光客がドラッグストアに殺到する事態となっています。これらは何も中国に限った話ではありません。この高い需要が、薬局ビジネスそのものへの関心につながっています。
実際、私の元にも、「薬局を買いたい」「日本の医薬品を海外に輸出するにはどういった許認可が必要か」という相談が来ています。
これらの相談者が、「地域医療の持続可能性と質の向上」という理念に従って行われることが望ましいのですが、実務の現場では必ずしもその理念が徹底されていない事例も見受けられます。
2. 後継者不足に悩む日本の中小薬局
日本では経営者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっており、事業の継続に悩む中小規模の調剤薬局が増えています。こうした状況が、事業を譲渡したい日本の経営者と、日本の薬局を手に入れたい外国人のニーズとを合致させています。
3. 参入障壁の低下
近年、外国語に対応できる行政書士やコンサルタントが増加しており、外国人が薬局を開設・買収する際の法的手続きのハードルが下がっています。SNS(WeChat等)では、薬局の売買情報や開業許可の手続き方法などが共有されており、外国人経営者同士のネットワークが参入を後押ししています。
買収後に発覚!横行する深刻なトラブル事例
問題は、買収そのものよりも、その後の経営で発生している数々の違法行為です。
トラブル1:医薬品の不正輸出・横流し
買収された薬局が、日本の医薬品を不正に海外へ流出させる拠点となっている疑惑が指摘されています。一部報道では、外国人経営者Aは、記者に対し、M&Aで薬局を買収し、母国で人気の市販薬を母国に送っていると認めた上で、正規の輸出に必要な煩雑な手続きについて問われると「特殊な流通経路がある」と述べるにとどまっていると報道されるなど、海外向け販売で必要な手続を回避しているかのような証言が示され、法令違反の疑いが指摘されています。実際、私の元にも、「友人が日本の薬局を買って、医薬品を海外に輸出するビジネスをしている」「専門家のアドバイスがあるらしい」という相談がありました。こうした行為は、国内で医薬品を必要とする患者への供給不足を引き起こすリスクもはらんでいます。
トラブル2:薬剤師不在の「無資格調剤」
最も深刻な問題の一つが、薬剤師の資格を持たない者による調剤行為(無資格調剤)です。薬剤師法では、薬剤師でなければ販売や授与の目的で調剤してはならないと厳しく定められています。 しかし、大阪府内では、薬剤師でない者が水剤の調整などを行っていたとして、薬局が業務停止命令を受ける事例が立て続けに発生しています。
大阪府における行政処分事例①(令和6年3月)
• 薬剤師でない者が長年にわたり調剤や服薬指導を実施。薬局は24日間の業務停止処分を受けた。
【処分理由】
(1)平成25年から、薬剤師でない者が、販売又は授与の目的で調剤を行っていた。薬局の管理者が保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、薬局に勤務する薬剤師その他従業者を監督していなかった。薬局開設者が薬局の管理者に薬局を管理させているとは言えなかった。
(法第9条第1項に基づく法施行規則第11条の8第1項、薬剤師法第19条、法第8条第1項、 及び法第7条第2項違反)
(2)薬剤師でない者が、服薬指導を実施していた。(法第9条の4第1項違反)
(3)薬局開設者が、従事者を区別するための必要な措置を講じていなかった。(法第9条第1項に基づく法施行規則第15条第1項違反)
(※「法」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律を指します。)
大阪府における行政処分事例②(令和6年7月)
• 薬剤師でない者が水剤の調整(直接計量・混合)を行っていた。これは薬剤師による途中の確認があったとしても薬剤師法違反にあたる行為であり、薬局は18日間の業務停止処分となった。
【処分理由】
(1)薬局開設者が、薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させていた。
(2)薬剤師でない者が、販売又は授与の目的で調剤していた。
(3)薬局の管理者が、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、薬局に勤務する薬剤師その他従業者を監督していなかった。
(法第9条第1項に基づく法施行規則第11条の8第1項、薬剤師法第19条、法第8条第1項)
(※「法」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律を指します。)
こうした無資格調剤は、国民の健康に直接的な危害を及ぼす極めて危険な行為です。
トラブル3:処方箋なしでの販売やずさんな管理
「大阪市は、処方箋医薬品を正当な理由なく販売した薬局に対し、45日間の業務停止処分を公表(2025年7月14日)。会見報道では“訪日外国人への販売”に言及がありました(業界紙報道)。」 大阪府薬剤師会は、本件行政処分を受けた事例に言及し、同様の不適切な販売が他にもあるとの認識を示しています。 また、平成29年1月、奈良県内の薬局において、C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品が調剤された事件では、医薬品の仕入れ段階での検査が不十分だったことや、管理者が業務を適切に監督していなかったことが違反概要として指摘され、業務停止命令が出されています。
なぜ違法行為はなくならないのか?
これらのトラブルの背景には、薬局開設者や役員の法令遵守意識の欠如や、ずさんな管理・監督体制があると考えられます。 厚生労働省は「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」を策定し、薬局開設者に対して、管理者の権限の明確化や、役職員の業務監督体制の整備などを義務付けています。しかし、利益を優先し、これらの責務を怠る事業者が存在するのが現状です。
まとめ
在日外国人による薬局買収は、後継者不足に悩む地域にとって一見すると救世主のように見えるかもしれません。しかし、その裏で医薬品の不正流出や無資格調剤といった違法行為が横行し、国民の健康と安全を脅かしている実態を見過ごすことはできません。 私たちの健康を守る医療インフラが、一部の不心得な事業者によって蝕まれることのないよう、行政による監視体制の強化と、薬局業界全体のコンプライアンス意識の向上が強く求められます。